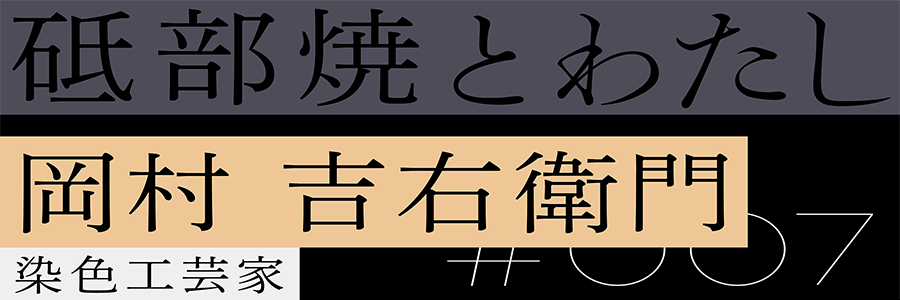ストーリーズ
砥部焼とわたし1977#007
ストーリーズ「砥部焼とわたし」
1777年(安永六年)に門田金治や杉野丈助らにより、砥部にて初めて磁器焼成に成功してから200年後の1977年(昭和五十二年)に砥部焼磁器創業二百年祭を記念して、発行された「砥部焼とわたし」。有名陶芸家をはじめ108名の方が、砥部焼との出会いや、つながりなどそれぞれの思いを綴った随想集を砥部焼協同組合の協力により紹介していきます。
砥部と鈴木繁男君と私
砥部に焼物がある。ということを知ったのは戦後である。はっきりとした記憶はないが、混乱期を過ぎて間もない頃だったと思う。当時、県の経済部長であった石川勉氏と民芸館で会った。愛媛県の手仕事を盛んにするため、下調べを鈴木繁男君がやっており、新作運動も平行して進められていて、その第一回の報告の時であったのではなかったかと思う。民芸館の広間に、鮮やかな磁器染付の食器の試作が一面に陳列してあった。磁器で、取り立てて云々するような普段使いの食器がなかった頃なので、皆大いに喜び、手にとって眺め、そして愛撫した。当然、反響も大きかった。安部祐工君もその時顔を見せていた。
第一回の出会いで、砥部の食器は私の家庭の中にも加わった。乱暴な使い方をしたが、丈夫で、かなり長持をした。愛用したのは猪口で、縁に割筆を打ったもので、随分と便利をしたし、訪ねて来た人も喜んで茶を呑んだ。今考えると、一つ位残しておけばよかったと惜しまれるが、手頃な器であったため、皆使い果たしてしまった。飯碗は竹の絵付けであったと記憶するが、それもない。
私が初めて砥部に行ったのは、東京民芸協会の人達と一緒に四国一巡をした時で、もう十五年位前になり、通り一片の見学であった。磁器の窯を見た最初になるが、その時鋳込みと呼ぶ型物に興味を持った。鋳込みは、轆轤と違って数物がこなせるが、形が鈍くなる欠点がある。それを何とか締った形に持ってゆこうと、鈴木繁男君が苦労を重ねていたのを聞いた。今もそうであるが、毎月磐田から砥部に通い、胎土、形、絵付けと、心を砕いてきている。時折会う鈴木君を通して、砥部の磁器について教わり、砥部への関心は鈴木君を通してのものである。砥部と鈴木君を別にして私は考えることはできない。熱っぽい鈴木君の話を聞くたびに、次第に砥部へ強く惹かれるようになってきたというのが実情である。たくみからその後手に入れて使う食器との直接的な繋がりより、むしろ鈴木君を通しての砥部の方が、私の心に深く食い込んでいる。
平凡社の仕事で、「日本の民窯」を書いた時、砥部の焼き物にはあまり触れていない。短い本文であったのと、古いものを書く必要からどうしても、北九州の通称伊万里の方に重点が移ってしまったためである。北九州の窯場を歩き、波佐見と大外山に興味を持ったことも事実であった。大外山は白絵掛けの捏鉢に松などの絵付けをしたものとばかり考えていたが、窯跡から、例外なくと言ってよい程磁器を焼いていたことを知って、陶器と磁器との繋がりを考えたし、三百も数えられそうな窯群と思える北九州の窯跡に圧倒され、他の磁器の窯場は一先ず、という考えになったのも事実である。然し、又、折があったら砥部を書こうという気持ちは心の底にあった。鈴木君が砥部でやっている仕事がいつも頭の中にあったのである。
一昨年、講談社から「民窯」の話が持ち上がり、水尾比呂志君と二人で東日本と西日本に分けて書くことに決まった。私は西日本を望んだ。西日本の方の窯をよく歩いているからである。最初、丹波以西ということになったいたが、水尾君の希望で、四国と九州に絞って欲しい、ということになり、引き受けた。私はいつもそうであるが、書く時には目の前に物があった方が書き易いし、現場を踏んだ時のノートも必要である。物がなければ写真を置いて眺めながらでも書くことはできる。然し、どうしても破片がないと困る。それも自分が歩いて、自分の手で拾った破片がないと駄目な性分である。破片を見ていると、歩いた時の窯跡の状態、仕事の話をして呉れた人のことが次々と蘇ってくる。つまり実感が湧いてくる。そのため、出来たら再び歩き直すことにしている。事情が許さなければ、二ヶ所でも三ヶ所でも、歩いていなっかた所を歩き、加えていくことにしている。誓い通り一片の訪問であっても、現場を踏んでいない所は書くのに気が進まない。仕事場というものは、何気なくてもよいから度々訪れることによって縁が深くなる。殊に、書こうと思うと一度きりでは何も彼も判る筈もない。二度、三度と訪れる回数が重なると、見落としていたことも拾い出せるし、身近にもなって安心して書ける。そのような訳で、妻と一緒に砥部を訪れることに決めた。この時も鈴木君に相談し、世話をして貰うことになった。
二度目の砥部行きで厄介を掛けたのは梅野武之助氏一門である。石切場の外山を始め、窯跡をつぶさに案内して貰ったし、仕事場も、参考書も見せて貰った。予備知識は鈴木君から十年この方聞いているので、それを実際に確かめ得たことになるが、砥部への関心は先ず北九州との関連であり、砥部に窯場が築かれて以後の発展の仕方、つまり砥部とでどのような工夫が試みられているかにあった。試作が成功している、していないかは私にとっては二の次で、試作そのものに興味がある。仕事をする時、何を考え、どんな工夫をするものなのかが、私の心を捉える。先に、破片を目の前にして書きたいといったのはそのためである。史実の示す通り、砥部の磁器は北九州の延長のなる。砥部だけでなく、日本の磁器は北九州の影響を直接、間接に受けない所は皆無であるが、一口にそれを伊万里に代表させてしまう傾向がある。ところが伊万里というのは甚だ厄介で、伊万里では焼き物を焼いていなく、商取引と積み出しが仕事になっていた。従って、北九州で焼いても、伊万里に集荷されないものは伊万里ではなくなる。どうも、伊万里という言葉は恐いと思う。実際に北九州の窯場を歩いて見ると、雑器の磁器は佐賀県より長崎県の方が多いと思うし、積み出し港はまちまちになっている。九州に限らないが、私が心を惹かれる染付雑器はくらわんかと呼ばれる一群で、初期伊万里とくらわんかは、染付とか磁器という言葉を聞くと直ぐに頭に浮かぶ名であり、好きな壺や皿を連想しもする。初期伊万里は必ずしも雑器ではなく、むしろ逆の場合がある。民窯となると、一応雑器を対象にしなければならず、そうなるとくらわんかを表に出すことになってしまう。私の関心はくらわんかと砥部との係わりにあった。
くらわんかを胎土が燻み、厚く、やや火度の低い素焼きをしない磁器の限定する人と、染付雑器を凡てくらわんかに入れてしまう人とあるが、その境は難しい。然し、くらわんかという名は、天草石を使っていなかった頃迄にものが私の頭の中にある。口には出さなくても、くらわんかは私にとって長崎県の三河内と波佐美のもの、という狭義の考えがいつもある。そして、砥部は長崎県の波佐見(大村藩)か三河内(平戸藩)の延長であろうことは、長崎県の窯場を歩いた時考え続けていた。この考えは、狭義のくらわんかが大体元禄を境にして天草石の移入が殖え、次第に影をひそめるようになっても、引き続いて焼いていた雑器の破片と照らし合わせて符合する。砥部で聞く長与の窯は大村藩に入る。然し、長与の窯跡は荒れており、このいい伝えを実証するのは難しい。
砥部の初期の窯跡から出る釉の厚い無地物は、佐賀県、長崎県を通じて出るものと区別は困難で、初期の試作が同じ段階であったのを物語る。白磁の雑器の優品は、北九州より砥部の方が多い。私は砥部と平佐のものが好きである。
また、小さな破片なので、断定は難しいが、極く薄く白化粧をし、粗画を描いた染付の破片がある。波佐見や三河内の窯跡からも、天草石を使わない以前に、胎土を白く見せるための工夫として、同じことをやっていたのを知っているし、砥部とは係りがないが、東北の切込みでも同じ手の破片を拾いもした。また、美濃でも、陶器の染付から磁器に移る過程で、陶土に白化粧をして染付をしたものは少なくない。どれも生掛け、つまり素焼きをしていないのも共通する。時代的には開きがあって、砥部が一番遅く、白化粧を他の窯から教えられた技法であるとは思えないが、仕事をする人間の共通性としてとても興味がある。
染付で目につくのは、当然のこと絵付けになる。絵付けの良し悪しは染付を決定してしまう。この絵付けは、ダミを入れない骨描きのものを除いて、画題に関しては北九州と変わりはない。茶碗や皿の見込みに、窯印と呼ぶ小さく簡単な模様が描いてあるのは、多くの人が目をつけた。美しさからいうと、見込みの模様の方が美しいことが多いし、器の形も引き締めもする。見込みの模様には変化が多く、楽しませて呉れるが、これで産地が判るとする人は可成りある。特徴的な柄が目につくからである。砥部もその例外ではないが、窯印と呼ばれる小さな模様は、果たして産地を示すものか、窯跡を歩いて疑問が湧くのである。砥部の雑器の窯印は三十を超えると思える数になるが、私が見たものの凡ては北九州で見ることができ、佐賀県、長崎県双方のものが入り混る。更に切込とも共通する。このことは、絵付けの工人が北九州から各地に散ったのを証明するとしか思えない。窯印に関してここで論考する気持ちはなく、何れも少し詳しく調べてから書く心算でいるが窯印は窯の区別をする目的ではなく、共同窯で見られる現象であるし、絵付工が複数いたことにもなると思う。絵付工の賃金を払うためや、共同窯で焼きあがったものの仕分けをする目的があったのではないかと考えられる。更に、五十なり百なりを描いた区切りに、柄を変え、勘定する目安にすることもあったと思えてならない。見込みの模様で窯を鑑定することは難しいということを九州で薄々感じてはいたが、砥部で確かめ得た、収穫になった。
砥部の絵付で、私の興味を惹くものはもう一つある。それは印版と呼ばれるもので、正確には型紙を素地の上に当て、上から呉須を摺り込む技法で、摺絵と呼ぶ。摺絵も北九州の小田志から始まり、美濃に移った。砥部で焼く様になったのはその後になろうが、他の窯でやらなくなっても、砥部では戦後も尚続いていたという。シャツ一枚で汗だくだくになって働いているような、そして一抹の侘しさのある染付で、二義的な絵付けとされるが、砥部の摺絵には力があって、私は好感を持っている。摺絵は関東では会津本郷があり、砥部も会津に入れられたり、その逆にされたりする。実をいうと、会津本郷には摺絵はなく、蚕養窯であるが、それは二の次として砥部の摺絵を机の上に置きたいというき持ちがある。
砥部の磁器で、浮彫りをし、上に飴釉や呉須を掛けたものも見る。これは平戸でよく目にするし、染付の清楚な味わいと違いもし、技術的にいうと嫌いなものではないが、優品は少ないのではなかろうか。染付以外で心に残るのは、梅野氏の資料館で、青磁に菊の花を呉須といっちんで側面から描いてあった猪口がある。絵に慣れもあるし、技術的に珍しいという種のものでもないが、可愛いい佳品という印象は消えない。これも傍に置きたいものの一つである。
一応の勉強はしたものの、いざ捶絵を選ぶとなると、いろいろと厄介な問題が出た。染付を入れたいし、そうすると呉須といっちんの菊絵も加えたい。随分と迷った揚句、一目でそれと思える染付はどうしても北九州になってしまう。白磁のものを砥部と平佐で代表させる結果になった。現在焼いている染付で、日本の染付雑器をとも思ったが、それも貢の大きさで割愛せざるを得ない破目になり、残念に思っている。白磁の撮影になった段取りで、次の著書の打合せ其他の雑用が重なり、またまた鈴木君に負ぶさることになった。目の利く鈴木君は、筆者の知らなかったものを加えて呉れた。安心はしていたが、予想よりずっと結果になったのは何としても有難いと思う。
砥部のことを考えるとき、梅野氏と鈴木繁男君抜きではどうにもならないのである。
岡村吉右衛門 / 染色工芸家
本書p19-24より引用
ストーリーズ「砥部焼とわたし」#008はこちらよりご覧ください。
1977年(昭和52年)出版「砥部焼とわたし」の随想集より
出版元:砥部焼磁器創業二百年祭実行委員会編
協力:砥部焼協同組合