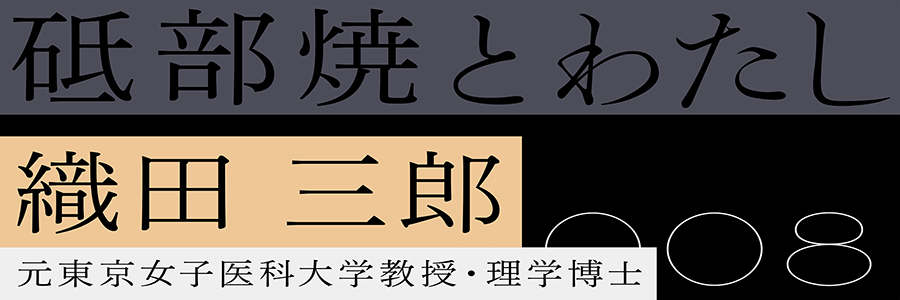ストーリーズ
砥部焼とわたし1977#008
ストーリーズ「砥部焼とわたし」
1777年(安永六年)に門田金治や杉野丈助らにより、砥部にて初めて磁器焼成に成功してから200年後の1977年(昭和五十二年)に砥部焼磁器創業二百年祭を記念して、発行された「砥部焼とわたし」。有名陶芸家をはじめ108名の方が、砥部焼との出会いや、つながりなどそれぞれの思いを綴った随想集を砥部焼協同組合の協力により紹介していきます。
尽きない懐かしい追憶
私は明治四十四年に砥部尋常高等小学校尋常科に入学、岩谷(いわや)の家から大南(おおみなみ)の小 学校までを六年間往復したが、その通学路には当時の砥部焼を想い出す懐かしい風物がいっぱいあった。その頃、岩谷から出かけるには、赤坂(アカサコといっていた)という小さい峠を越えることになっていた。 赤坂は、岩谷の方からの登りは大した坂ではなかったが、岩谷口の方への降りは急な坂であった。その岩谷口へ降りた所に守本窯があったが、その近くに白い粘土をかなりの規模で採掘した所が二、三ヵ所あった。 この粘土を焼物に使ったかどうかは確かでないが、少なくとも窯の造成などには使用したと思われる。この粘土は軟質で、水を加えて練るだけでよかった。この粘土は、またわが家の壁土を作るのにも用いられたので、日曜日など父の命令で、よく採りに行かされたものである。
守本窯は当時かなり手広く営業していたようで、道路わきの広い面 積に、原料石粉の水撥場や泥漿乾燥場などが造られていた。また成形. された茶碗などをたくさん板の上にならべて日乾する作業場が道路の すぐ近くにあって、その茶碗などをならべた板を上手に手の上にのせ て持ち歩く職人の姿を毎日のように見ていた。
守本窯を通り過ぎて、 旧庄屋の日野家の長い白塀を右に見て、道は 、やがてだらだらと砥部川へ降ってゆく。そこに橋があって、橋のたも 棒です とに大水車場があった。その付近は屋根も道路も草原も、白い粉で一面にまっ白になっていた。小学校へ通いはじめた頃は、この白い粉が どういうものかさっぱり見当がつかず、ただ水車場の近くはもやもや と白煙が立ちこめていたので、鼻をつまんで走り抜けたのを覚えてい. る。この水車場で砥部焼の原石を搗き砕いて石粉を造っていることを知ったのは、ずっと後になってからであった。
砥部川を渡って、坂を上ったところが客(きゃく)というところで、そこに大きなムクノキが一本あった が、そこが焼物の廃品の捨て場となっていた。そこから砥部川へ焼成不良品や使用できなくなった窯道具な どが多量に投棄されたようで、遠くから眺めると白い土の滝のようであった。この廃品の中には、子供の遊 び道具として格好のものがあったので、学校の帰りによくここで道草を食ったものである。
そのころ一般に焼物のことを「唐津」といい、それを造る所を「唐津山」と呼んでいた。当時の窯はたい てい登り窯で、丘陵地に造成されていたので、「山」といったのであろうか。また燃料はもっぱら赤松の割木 で、窯に火が入ると、身ぶり面白く松割木を窯に投げ入れる人の姿が、まっ赤な火焔にはえて、いかにも男 らしい作業にみえた。
松割木はたいてい馬の背で運ばれた。割木を馬の両横腹から背の上へ山のように積みあげた馬を、馬子は 「きせる」でもくゆらせながら、鼻うたまじりに引いて行く風景は、田舎道にふさわしい、のどかなもので あった。
このような懐しい追憶は尽きないが、あの頃からもう六十年以上も経過しており、砥部も砥部焼もいろ いろの点で変わってしまった。私もたまに郷里へ帰るだけで、現在の砥部焼については何も知らない。
さて私は、砥部町教育委員会編集の「低部焼の歴史」という本が昭和四十四年に刊行されたことをとても 嬉しく思う。この本には、初期の美しい砥部陶磁器の写真や砥部焼に関係ある懐しい資料・遺跡の写真な どがたくさん入れてあって、本をばらばらとめくるだけで、けっこう楽しめるが、暇なときしっくり読んで みると、いろいろのことを教えてくれる。その中で私が最も引きつけられたのは、砥部磁器創業の経緯であった。以下に多少私の勝手な想像も加えて簡単に書いてみる。
そもそも「砥部」というのは磁石を産出する部族、または部落という意味であろう。砥部磁器が外山(と やま)の砥石から創まったという事実はまことに興味深い。年表によると、底部の底石は伊予砥といって、 天平十九年(七四七年)の正倉院文書に記載されているほど、古くから知られていたが、安永四年(一七七 五年)の頃、低部は大洲藩に属し、大阪淡路町の砥石問屋和泉屋治兵衛というのが砥石の販売元であった。
当時わが国の磁器創業の地、肥前においては、さきに酒井田柿右衛門による赤絵の技法革新などもあって、 磁器業界は大進展をし、国内のみならず、オランダ貿易にまで利用されていた。和泉屋は、肥前磁器の一部 が天草砥石を原料としていることを知って、砥部外山産の磁石屑を利用して、この地に磁器創業が可能であ ることを大洲藩に進言した。
当時の第九代大洲藩主加藤泰候(一七六OI! し)は藩の殖産興業の一環として、砥部磁器創業を決意。藩は和泉屋のあっせんで、肥前大村藩から五人の陶工を雇い入れ、藩の御用油商、麻生(あそう)の門 田金次を企業主幹とし、磁器焼造の直接監督には原町(はらまち)の杉野丈助をあてた。諸般の準備をして 安永四年(一七七五年)三月焼成に着手、試焼数回、磁土、釉薬とも火度に不適で失敗。同年十一月、本焼 成にかかったが、ことごとく失敗。肥前大村藩の隔工五人も失望帰国。丈助の苦心は言語に絶したが、翌五 年十二月、再度の窯焼に火入後三昼夜経過、釉薬不栓、薪は焚き尽し、窯屋の社まで焚くその効なく、丈助の姿は狂ったようにみえたという。 外たまたま筑前上須恵より来年の信吉なる者が、失敗の原因は釉薬にあることを指摘した。丈助はその勧め 県によって、翌安永六年十月筑前の地に釉石その他を求めて帰り、同年十二月、新釉薬を用いて、ついに外山砥石の焼成に成功、これが砥部磁器の最初のものとなった。今からちょうど二百年前のことであった。
砥部焼の味わいは、何といってもまず、あの淡黄磁のまろやかな感触であろうと私は思う。
それはともかく、二百年も前に天草砥石と砥部砥石をならべてみて、やがてハタとひざを打ったであろう和泉屋治兵衛に敬意を表して概文を終る。
織田 三郎 / 元東京女子医科大学教授・理学博士
本書p25-28より引用
1977年(昭和52年)出版「砥部焼とわたし」の随想集より
出版元:砥部焼磁器創業二百年祭実行委員会編
協力:砥部焼協同組合