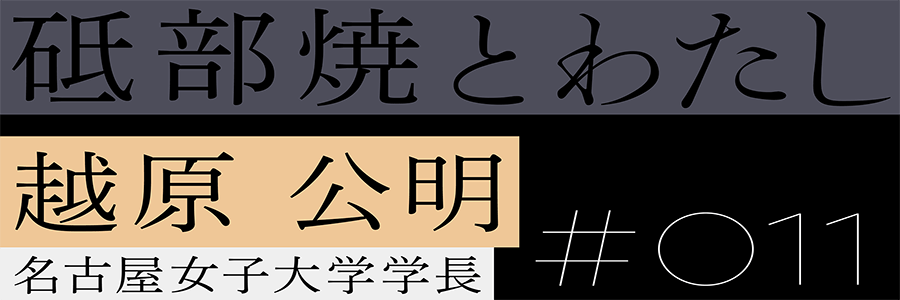ストーリーズ
砥部焼とわたし1977#011
ストーリーズ「砥部焼とわたし」
1777年(安永六年)に門田金治や杉野丈助らにより、砥部にて初めて磁器焼成に成功してから200年後の1977年(昭和五十二年)に砥部焼磁器創業二百年祭を記念して、発行された「砥部焼とわたし」。有名陶芸家をはじめ108名の方が、砥部焼との出会いや、つながりなどそれぞれの思いを綴った随想集を砥部焼協同組合の協力により紹介していきます。
少年の日と砥部焼
淡黄磁
もう五十数年、半世紀以上も前のことです。大正七・八年という、ぼくが十二・三才の少年淡黄磁の頃のなつかしい想い出です。
砥部村五本松で医者をやっていた父の阿部正剛が、安息日などに、座敷の応接机の上に焼き物を並べ、じっと見入っていました。大変楽しそうです。
ある日その部屋にぼくを呼び入れて、陶磁器考がはじまりました。
「公明、この蓋付きの茶碗はな、淡黄磁といって明治中頃の先代向井和平窯のものじゃ。見ろ、何ともいえん味じゃろ。この地肌の溶けるような淡い黄色が何ともいえん。それが、いまはもう出来んのじゃ」
「どして、いまは出来んのですか」
「なんとかして、この味を出したいと思うて何度かやってみるが、どうしても出来んようじゃ。特に土のあんばい、それに職人、うわ薬、焼き方などにいまでは真似られたものがあるのじゃ……」
焼き物がそんなデリケートなものだと、はじめてぼくが知ったのは、この時です。
「公明、磁器と陶器の区別を知っているか」
「知りません」
「一口に砥部では、焼き物とか唐津物と呼んでいるが、この焼き物に磁器と陶器の区別がある。磁 器は千五百度近い温度で焼き上げるが、陶器はそれより三・四百度低い温度で焼いたものじゃ。お前は、焼き物ところの砥部村に生れたのだから、しっかり覚えておけ」
「はい」
それから話は徳川期の古砥部にまで及びました。
この父と対話のひと時は、いまもってはっきりと印象に残っているのです。……先代向井和平、淡黄磁。千五百度近い、それより三・四百度低い。 磁器、陶器。古砥部。
馬追いさん
当時、窯業に一番大切な陶石や陶土、それに燃料の松割木は、そのほとんどを馬の背に乗せて運んでいました。 陶石や陶土は木桶に入れ馬の背に振り分けて二桶ずつ、松割木は適当な長さの原木をそのままか割木にしたものを、これまた背に振り分けて運びます。馬追いさんと呼んでいた馬子がこれを追うのです。
こうして馬たちが、ひねもすあちらの山あい、こちらの山あいを、馬追いの鼻唄とともにぽっりぽっくりと蹄の音をさせながら登り降りします。月の砂漠をはるばると旅のらくだがゆきました、にはあらねど、 正に牧歌的で夢ゆたかな風物詩でしたよ。
その一つに西大谷池に沿った山路から、ぼくの家の東側まで運んで、そこにある薬葺きの中継小屋に荷を降ろすという、主要運搬路がありました。ここから森へはまとめて馬車で運んでいたようです。その馬追いのNおいさんは、いつも顔を合わせているうちにぼくと大の仲よしになっていました。「おいさん」と呼んでいました。
ある夏の日、例のように馬を追いながら西の谷沿いの緑の木立を見えかくれしながら降りてきたおいさんが、ぼくと顔を合わせるなりいいました。
「ぽっつあん、あの畑の赤い実は何ぞな」
おいさんの指は、ぼくの家の畑になっている赤い実を指差しています。
「西洋なすじゃがな」
この西洋なすは、後でトマトと呼ぶようになったもので、父が松山の知人から種をもらって初めて作ったものです。赤い実がたくさんついたのですが、あのトマト特有の異様な匂いに家の者は勿論、近隣誰ひとり 食べ手がありません。
つづいておいさんは「食べれるけ」とききました。
「うん食べれるけど、臭うて誰もよう食べんのじゃがな」
「そうけ、おらに一つくれておみや」
「臭うてもよかったら、何ぼでもお食べな」
おいさんは、大きなトマトをもぎとって一口がぶりとやるなり「こりゃうまい」がぶりがぶりとやってしまった。びっくらこいだのは、少年のぼくです。
「だあれも食べる人がないのなら、お母さんに頼んで、みんなおいさんにもろうとおくれや」
「うん、待っといで、いまきいてくるけん」
母は快く「なんぼでもおあげや、青いのも熟れてきたら、いつでも持っておいきといっておあげ」こうしておいさんは、あと一月以上西洋なすをご馳走になったわけです。後年ぼくは、ぼくの大好物になったトマトを食べながら、相好を崩して西洋なすを頬張った、あの馬追いのNおいさんの顔を思いおこすのです。
学習
その頃五本松にあった三つの窯元を下山(しもやま)、上山(かみやま)、奥山(おくやま)と呼んでいました。秋から冬にかけて、そのいずれかの窯に火が入ると、それはぼくたち子供の天国でした。夜を待って芋焼きに出かけるのです。薩摩芋を懐にやんちゃ坊主たちが七人、八人と登窯の赤い焚口に集まってきます。それぞれ芋を窯の外まわりに並べ立てて三・四十分、こんがりとほどよく焼き上げるといった寸法です。
ところで、この三・四十分がぼくたち少年にとっては、すこぶる有意義な学習の時間だったわけです。窯のまわりで何をそんなに勉強したかっていわれるとちょっと困りますが、それは窯たきのおいさんから受ける各般の講義だったわけです。窯たきのおいさんは数人いましたが、そのうち、A、B、Cの三人のおいさんは、それぞれの専門科目をマスターした一流の講師でした。Aおいさんは社会学各論担当で、ぼくたちのもちだす世上のいろんな問題や疑問を即座に解答してくれました。日露戦争に従軍したBおいさんは歴史学担当で、広瀬中佐からはじまって忠臣蔵、水戸黄門漫遊記とレパートリーは十本以上もあって、時々浪花節 が交っていました。ところでCおいさんなんですが、Cおいさんは性教育担当で、これは家でも学校でもきくことの出来ない貴重にして、しかもらっしもないセックスの講義でした。だがCおいさんは必ず講義の最後に「おまえら、わしの話きいてそんなまねしちゃいかんぞ。大人になったらええけどのう」と訓戒も忘れませんでした。このCおいさん担当の夜が特に賑わったようにおぼえています。
Cおいさんは身振り手振りの有益な講義をつづけながら、時々焚口を開けて松割木を投げ込みます。都度十本あまりの割木を、ひふみよいむなやここのとうと、全く何センチとくるわぬ等間隔に投げ入れるのです。 めらめらと割木は炎をあげて燃えあがります。少年たちと窯たきのおいさん、こうしたメロドラマの中に夜は更けてゆきました。ぼくたちは焼き上った芋を懐に、片手で芋を頬張りながら、にぎやかな下山です。「C おいさんは猥談うまいのう」「そやけど、あんな話聞いたことが先生に知れたら、えらいめにおこられるぞよ」 少年たちは、それぞれ家に散ってゆきました。
願うこと
ここ創業二百年の砥部焼が、伝統的工芸品の指定を受けたことは何とも嬉しいことです。未来に向って、この栄誉をますます輝かしいものにしてゆかねばなりません。
思うことですが、これを期に日展級の陶芸作家がどんどん出てほしいものです。
砥部村を出て幾十年、いま瀬戸、多治見、常滑という陶磁どころにとり囲まれた名古屋に生活しているほくは、いきおい日展陶芸作家にとり巻かれていることになります。 日展会員や審査員級の作家だけでも枚挙にいとまなしといったところです。曰く加藤唐九郎、鈴木青々、加藤紗、河本五郎、加藤舜陶、大江文象、小林文一、加藤卓男、黒田耕三郎、亀井勝等の諸氏にはじまって中堅や新進作家が目白押しです。ぜひ一つ砥部焼の分野からも、毎年日展の会場に数人の作家名が並ぶようになってほしいものです。
ぼくの親しい大学教授の息子さんが、数年前瀬戸窯業高校に入りました。当時その友人から「息子はおやじの歩いた学者コースを失礼して、窯業高校へ入りました」と聞かされたとき、中卒の少年がなかなか思い切った将来設計をしたものだと思いましたが、またたく間に年月は巡って、窯業高校を出るや続いて三年連続の日展入選です。加藤紗氏に師事していると聞きます。名は青木鵬磨君、ギリシャの吟遊詩人ホーマにちなんで自らが命名したそうです。会ってみるとまだ初々しい青年です。 いよいよ伝統的工芸品砥部焼の隆昌を祈念するとともに、重ねて日本的工芸作家の誕生を願ってやみません。
越原公明 / 名古屋女子大学学長
1977年(昭和52年)出版「砥部焼とわたし」の随想集より
出版元:砥部焼磁器創業二百年祭実行委員会編
協力:砥部焼協同組合